はじめに

みなさん、こんにちは
ども、せっけんです
今日はぼくの最近読んで面白かった本を紹介させていただきます~~~
突然ですが、、、、
みなさんの周りにこの人優秀だなあと思う人っていますか?
ぼくが身の回りの優秀な人を思い浮かべてみると、ある共通点があると気が付きました
成長したいけど、どうしたらいいのかわからないというひとに向けて、ちょっと成長するきっかけになればうれしいなと思います
今日はそんな昨日までの正解が明日の正解とは限らないこの世の中でとっても必要な力だと思う「具体と抽象についておススメしたいと思います
具体と抽象
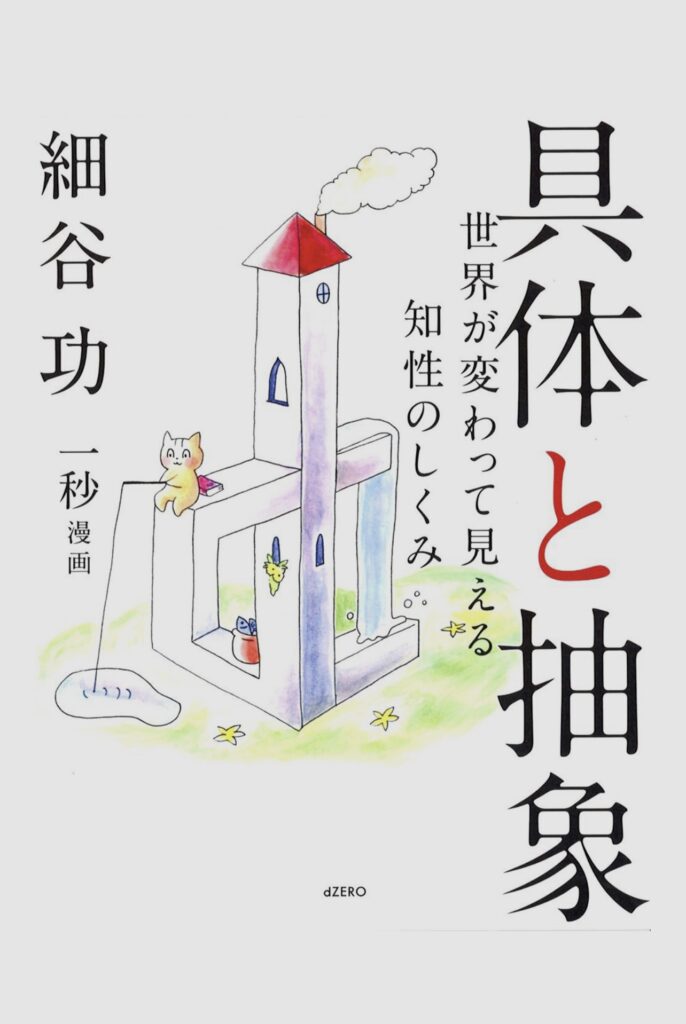
- タイトル:「具体と抽象」-世界が変わって見える知性のしくみ-
- 著者:細谷 功
- ¥1,426(Kindle版-電子書籍-)
- 序章 抽象化無くして活きられない
- 第1章 数と言葉
- 第2章 デフォルメ
- 第3章 精神世界と物理世界
- 第4章 法則とパターン認識
- 第5章 関係性と構造
- 第6章 往復運動
- 第7章 相対的
- 第8章 本質
- 第9章 自由度
- 第10章 価値観
- 第11章 量と質
- 第12章 二者択一と二項対立
- 第13章 ベクトル
- 第14章 アナロジー
- 第15章 階層
- 第16章 バイアス
- 第17章 理想と現実
- 第18章 マジックミラー
- 第19章 一方通行
- 第20章 共通と相違
- 終章 抽象化だけでは生きにくい
永遠にかみ合わない議論、へいとスピーチ、ネットでの大炎上。その根底にあるのは「具体=わかりやすさ」の弊害と「抽象=知性」の危機。動物にはない人間の知性を支える頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から検証。具体的言説と抽象的言説のズレを表現
「BOOK」データベースより
ビジネスコンサルタント。1964年、神奈川県に生まれる。東京大学工学部を卒業後、東芝を経てビジネスコンサルティングの世界へ。アーンスト&ヤング、キャップジェミニなどの米仏日系コンサルティング会社を経て、2009年よりクニエのマネージングディレクターとなる。2012年より同ysあコンサルティングフェローに。専門領域は、製品開発、営業、マーケティング領域を中心とした戦略策定や業務/IT改革に関するコンサルティング。併せて問題解決や思考力に関する公園やセミナーを企業や各種団体、大学などに対して多数実施している。 著書に、『頭力を鍛える』(東洋経済新報社)、『いま、すぐはじめる地頭力』(だいわ文庫)、『「Why型思考」が仕事を変える』(PHPビジネス新書)、『象の鼻としっぽ』(梧桐書院)、『アナロジー思考』(東洋経済新報社)、『会社の老化は止められない』(亜紀書房)、訳書に『プロフェッショナル・アドバイザー』(デービッド・マイスターほか著、東洋経済新報社)、『ハスラー』(アリ・カプラン著、亜紀書房)などがある。
「BOOK著者紹介情報」より
この本からの学び3選
ぼくがこの本を読んで、学びに感じた部分をご紹介させていただきます。

この本を読んで、「抽象化」の根本は「物事の共通点を見つけること」といえると理解しました
個人的には、お笑い芸人キングコング西野さんがとても上手な部分だと思います。
作品を売るのは、こんなにも多変だけれど、人は毎日何かを買っているわけだ。米、パン、水、牛乳・・・値段が高くても、テレビ、エアコンだって買っている。なるほど、<生活必需品>は買っているわけだ。
人がモノを買う(買われやすいモノの)線引きが、ここで明確になった
パンや水は必要だけれど、僕の絵本なんて生きてく上で、それほど必要ではない。売れにくくて当然だ。
ならば、少し手を加えて、僕の絵本を<必要なモノ>にしてあげればいい
~(中略)~
人は作品にはお金は出さないけれど、思い出にはお金を出す。事実、これだけ時代が変わって、いろんな仕事がロボットに代替されなくなっていくのに、「お土産者さん」は強も元気だ。
僕らは何故、「おみやげ」を買うのだろう?
それは、「おみやげ」が思い出を残す(思い出を思い出す)装置として<必要>だから
つまり、「おみやげ」は生活必需品で、米やパンや牛乳といった、そちら側に分類されていたわけだ。そりゃ売れるよな。
ならば、自分の作品を「おみやげ化」してしまえばいい。
「おみやげ化」する為には、その前段階として、「体験」が必要だ。宮島や、シンガポールや、演劇のような
キングコング西野オフィシャルダイアリー「魔法のコンパス」 「体験×おみやげ」の時代へ
上記は、彼が「自分の絵本を売るため」に「世の中で必需品ではないけど、売れ続けているモノ(宮島のペナント、シンガポールのマーライオンの置物、演劇のパンフレット)」の共通点(法則)を「おみやげ(思い出を思い出す装置)」と抽象化して、その法則を絵本に置き換えると「体験が必要」と具体化している、抽象化⇔具体化の好事例です
イメージ的には、「世の中で成功している人の共通点を見つけることで、成功するために必要なことを見出す」みたいなことですかね。本を読んだからできるようになるわけではないですが、この全体像を把握することで、普段の生活の中で練習できる部分がたくさんあると思います

みなさんも経験があると思いますが、「この人と意見が合わないな~」となった時によくあるのが、「お互いに話している、粒度や想定しているシーンが違う」なんてことではないでしょうか
具体的な話と抽象的な話を自由に行き来しながら、考えられるようになると、「どこで話が食い違っているのか」、また「相手はなにに引っかかっているのか」などが客観的に把握することができるようになります。
なので、異なるバックボーンを持った人とも、建設的に話を進めることができるようになると思います
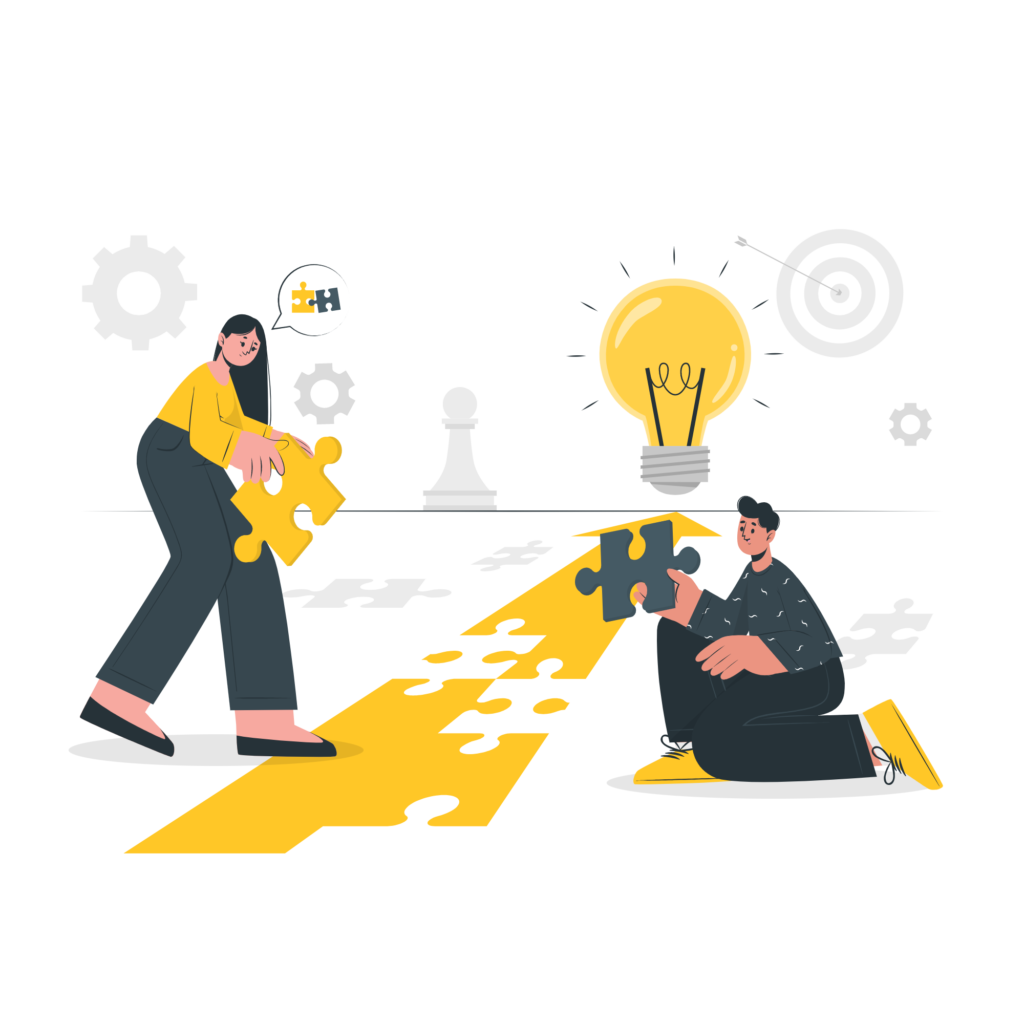
一つ目でもお伝えした、「抽象化の根本は、物事の共通項を見見つけること」をうまく実践するために、そのために必要なステップとして「重要な部分はなにか?を把握すること」だと思います。
具体と抽象を旨く行き来できるようになると、必要な要素を把握できて要約してお話することもできますし、逆に具体的な事例を挟んで、丁寧に話をすることもできます
用意された時間に合わせて話す機会は社会人になると結構あるのではないでしょうか?そんな時に、薄い話しかできない、、話が長くなってしまう・・といった悩みを持つ人にお勧めかもしれません
まとめ

みなさんいかがだったでしょうか?
仕事だけではなく、プライベートにおいても役立つ考え方が詰まった一冊だと思います。この本を読めばすぐにできるようになるわけではありませんが、かなり具体的なエピソードを踏まえて、体系的に書いてくれていますので、すごく参考にしやすい一冊だと思いました
気になった方は是非読んでみてください!
では、また!

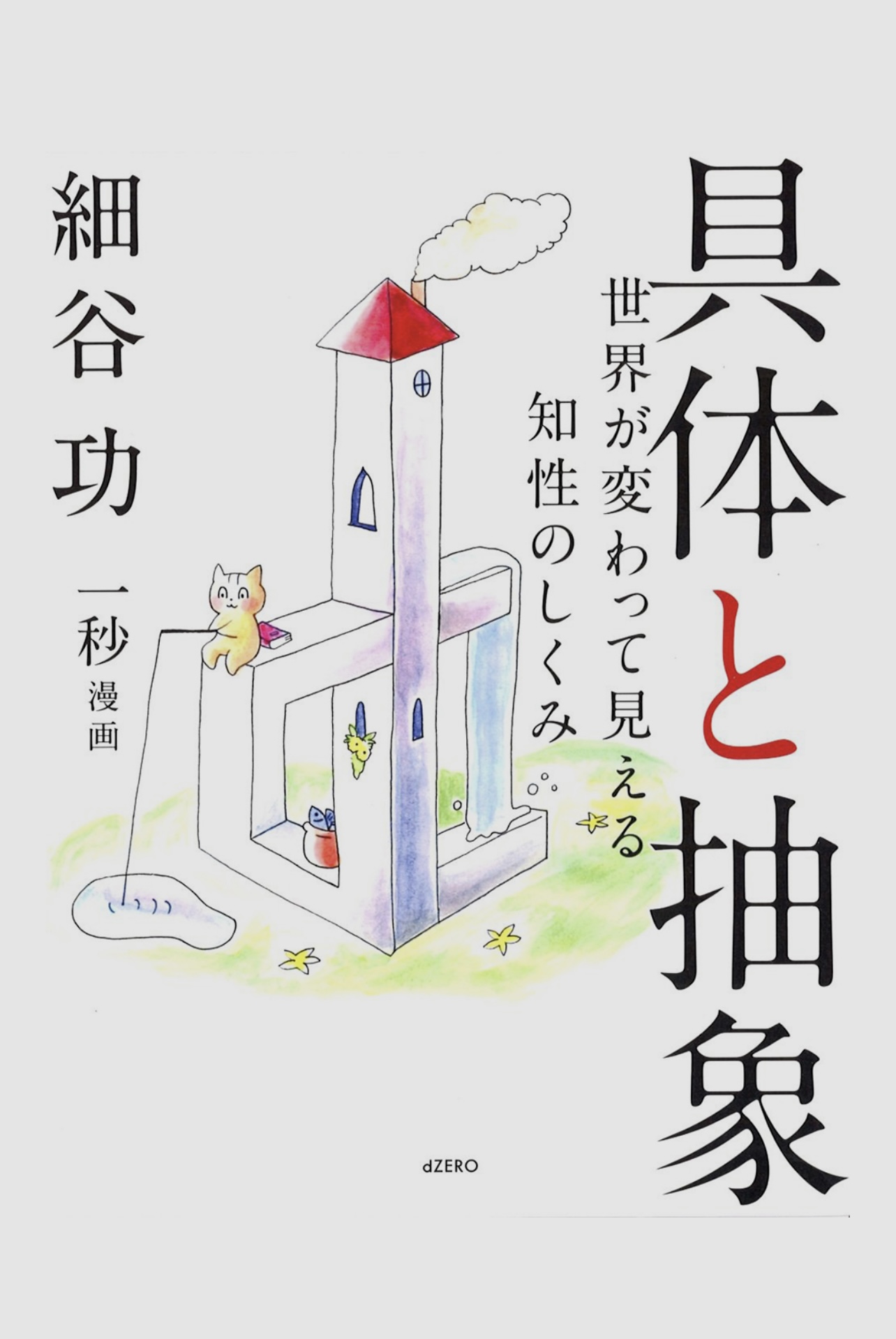


コメント